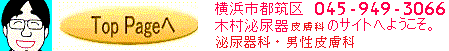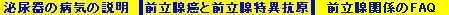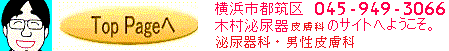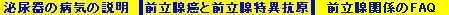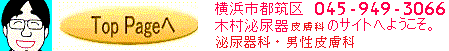
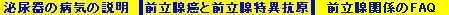
日泌総会82回
CAPDの継続が困難となりHDに移行した腎不全患者4例の検討
都共済青山
木村明,藤城徹幸,内田健三,上谷恭一郎
CAPDが血液浄化療法の1つとしてわが国に普及して10年以上が経過し,安定した治療法として定着している.しかし,一方で長期化に伴う腹膜機能の低下といった問題も出てきている.当科では,1985年より1993年まで,41例の腎不全患者に対し,CAPDの導入を行ってきた.このうち,現在も当院でCAPDを施行中のものが17例で,その他の症例の内訳は,急性腎不全に対し短期間のみCAPDを施行したものが1例,原疾患や合併症等によりすでに死亡したものが14例,CAPDのまま他院に転院したものが5例,除水能の低下等によりHDに移行せざるを得なかったものが4例である.今回は,この4例について報告する.
4例のうち3例は除水能の低下によるものであった.
症例1:54歳,男性.原疾患は慢性腎炎で1986年よりCAPDを開始.1.5%ダイアニール2L,1日4回の交換で,800ー1000mL程度の除水が得られ,導入後4年間は除水量が減少することなく,経過していた.
1990年8月6日,腹膜炎を起こし入院.入院時には,40℃の発熱,強度の腹痛,さらには血圧低下や白血球・血小板の減少といった菌血症を疑わせる重篤な状態であった.起炎菌は,ペニシリン,セフェム,ニューキノロン,アミノグリコシド等に感受性のある黄色ぶどう球菌であったが,これらの薬剤を全身投与および腹腔内投与するも,下熱に3週間を要した.CAPD排液は,培養では7日目より菌が陰性化(ただし,検体採取時も化学療法は続行していた)したが,排液の混濁は9月上旬まで続き,抗生剤の腹腔内投与を続けた.
8月末には,腹痛,発熱等の腹膜炎症状はなくなったが,この頃より除水量が300mLに減少し始めた.9月下旬には,下腿浮腫を認めるようになったため,CAPD液を高濃度の2.5%ダイアニール2Lに変更した.これにて600mL程度の除水が得られ,10月18日退院となった.
しかし退院後も除水量の減少が続き,1991年3月には4.25%ダイアニール2Lを1日4回交換しても 200mLの除水しか得られなくなり,下腿浮腫が顕著となり,1991年7月血液透析に移行した.
CAPDチューブは抜去せず,6ヶ月の腹膜休息の後,1992年2月より2.5%ダイアニール2L1日4回の交換を再開したが,1日200mLの除水しか得られず,血液透析から離脱できなかった.
症例2:66歳,男性.原疾患は慢性腎炎で1985年よりCAPDを開始.1年目には除水量が1000ml/day程度あったが,1年ごとに100ー200ml/dayずつ除水能が低下し,1992年には200ml/dayの除水しか得られなくなった.そのころは尿量が700mlあったが,1992年には尿量も200ml程度となり,下腿浮腫を認めるようになった.1993年には浮腫が顕著となり,胸水も認めるようになったため,HDに移行した.症例3:55歳,男性.原疾患は慢性腎炎で1988年よりCAPDを開始.1.5%ダイアニール2L,1日4回の交換で,1000ー1500mL程度の除水が得られいた.導入2年目より年1回腹膜炎を併発したが,3年間は除水量が減少することなく,経過していた.
1992年2月からは毎月のように腹膜炎を生じるようになった.起炎菌は,どの抗菌剤にも感受性のあるぶどう球菌であるかもしくは陰性で,抗生剤の腹腔内投与を数日行うことで軽快退院するが,1ヶ月後には再発するということを繰り返した.CAPDカテーテルが感染巣になっていることを疑い,11月カテーテルの入れ替えを行ったが,1週間後には再発した. また,11月頃より除水量が500ml/day程度に減少した.
1992年12月30日に発症した腹膜炎では,除水が得られず,出納がマイナスとなったため,1993年1月4日よりHDを併用した.腹膜炎軽快後も除水能は回復せず,1月13日AVシャント造設し,HDに移行した.
残り1例は,CAPD導入直後に横隔膜交通症を生じた症例である.
症例4:37歳,男性.で,導入8日目より排液不良となり胸部X線撮影にて右側のみに胸水を認めた.99mTc-MAAを腹腔内に注入して行ったシンチグラフィーで胸腔内への移行を認め横隔膜交通症と判明.胸腔内自家血注入による胸膜癒着を数回試みるも不成功のため,CAPDを断念し,HDに移行した.