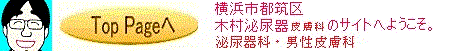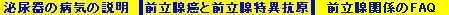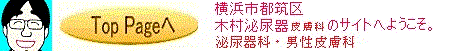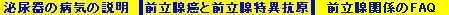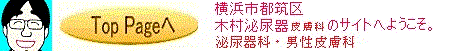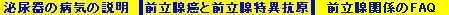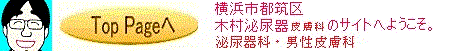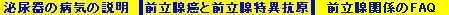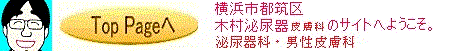
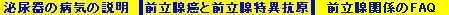

私の著書 「尿の悩みを解決する本」 <教育書籍> (千円) の下書き原稿
に入るほどうまいわけではありません.手術に関しては人なみです.
そもそも,ある程度経験を積んだ医者同士でどちらが手術が上手かなどは,何を基準にするかで変わってきます.手術時間が短く,出血量が少なければ,それが全てという訳ではありません.確かに手先は器用な方が良いでしょうが,職業としていつも手術に携わっているわけですから,天性の器用さが,技量の差としてでることはありません.医者が主人公のテレビドラマのような天才外科医はいないのです.
ただし,内視鏡手術はごく最近まで,名人から弟子にマンツーマンで教えるしかない,特殊な技術でした.私が学生のころには,膀胱鏡に接続できるテレビカメラがなく,泌尿器科の手術実習に行っても,術者が患者の股の間に入って,内視鏡を操っているのが見えるだけで,中は見せてもらえず,それは退屈な実習でした.そのころの内視鏡手術の指導は,新米とベテランが交互に,股の間に座って,まずベテランが”尿道口の右手前のこのでっぱりをとりあえず三掻きほど削れ”と言ってから席を新米に譲り,言われたところまでやったら,またベテランに替わるというものでした.肝心なところになると,ベテラン自身が削り,時々新米に覗かせてやると言った,調子で教えるので,一人の医者を育てるのに一人のベテランが十回くらい指導しなければなりませんでした.ですから,内視鏡手術の名人のいる病院に回った医師がその技術を早く身につけ,若手医師の間で最も差がつく技術でした.?ページに紹介した医師たちは若い頃,東京逓信病院の前部長だった岩動孝一郎先生(現大阪医大教授)や板橋にある大和病院の細井康男先生といった名人の指導を直接受けることができたラッキーな人達です.
テレビカメラの小型化により,今では,内視鏡手術の指導は,新米に削らせながら,ベテランがテレビを見て,注意することが出来るようになり,効率が良くなりました.受持ちでない医者も手術が見学できるようになり,実際に執刀しなくても,勉強できるようになり,名人芸ではなくなってきました.そして,学生は退屈せずに手術を見学できるようになりました.
さて,やっと本を一冊書き終えることができました.超音波や結石破砕の解説書など,医者向けの本の一部だけなら,何度か書いたことはありましたが,一冊の本をまるまるひとりで書き上げるのは今回が初めてです.
後は,この本が評判になって,両親の住む広島県府中市の小さな本屋にも並んでくれると,最高の親孝行になるのですが.一番心配なのは,このシリーズの中で,この六巻だけが大量に売れ残り,教育書籍にご迷惑をおかけすることです.今は,発売される日を,不安とともに待っています.
最後に