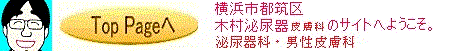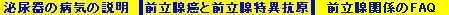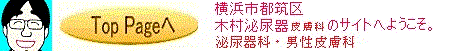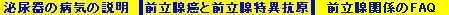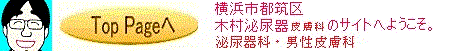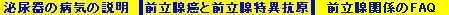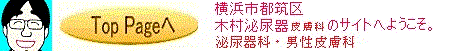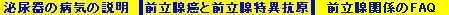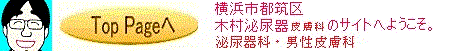
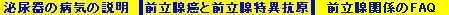

私の著書 「尿の悩みを解決する本」 <教育書籍> (千円) の下書き原稿
診療方針(自己紹介)
・診断は最新の方法で,治療は定評のあるもので
説明を読んだり聞いたりして良いと思った新しい診断法は,早く取り入れるようにしていますが,新しい治療法はその評価が定まってから取り入れるようにしています.
それは,診断法にしろ治療法にしろ,始めた人たちは,良い事ばかりを報告し,すぐに真似た人たちも,新しい点に目を奪われて欠点をあまり重視せず,数施設で行われるようになって初めて良い事だけではないことが聞こえてくる,ということが,間々あるからです.
では,診断法も評価が定まってからで良いではないかと,言われそうですが,診断法に関しては,仮に新しいものが期待されていたほどでなくても,患者さんへの迷惑は時間の無駄だけで済み(多くの場合,新しい検査法は,診療報酬を請求できませんから,費用の余分な負担はないはずです),むしろそのおかげで今までの辛い検査を受けずに済むことが多いように感じているからです.
・検査のスケジュールは緩急自在
大学病院や国立のセンター病院では,診断や治療法決定に必要な検査は最初のうちにまとめてやることが多い傾向にあります.これは,すでに近医で治療は受けていて,確かな診断とより高度な医療を求めて来る人が多いという患者さん側の事情と,外来担当医が次々と交代するので,必要な検査がやられずじまいとなり,重大な病気を見落としてしまう危険を避けるため,必要な検査は早く終わらせてしっかりとした診断を付けておこうという病院側の事情によるものの相乗作用の結果です.
私自身は現在大学病院に勤めていますが,東芝病院,東京都職員共済組合青山病院のような職員が最初にかかる病院に長く勤めていました.そこでは悪性の病気を否定するためにいきなり辛い検査はしない方針でやってきました.例えば,前立腺肥大症らしい症状の人が来たら,最初は簡単な検査だけで,とりあえず,内服薬を出してみて,2週間後の満足度を聞いてから,手術するかどうかの決定に必要な検査をやるようにしていました.
両方のタイプの病院に勤めた経験のおかげで,患者さんが,とりあえず症状を取ってほしくて来院したのか,徹底的に調べてほしくて来院したのか,はなしの中から感じとって,できるだけ患者さんに満足してもらえるよう努めているつもりです.